パソコンの性能表やカスタマイズに用いられる、実用される用語を中心に解説しています。
メモリの用語
メモリ

パソコンが作業に使うデータを一時的に置いておく場所。たくさんあれば多くのデータを素早く出し入れできるので動作が安定する。少ないといずれ一杯になり、メモリより遅いストレージ(長期的な保存場所)からデータを取ってこなければならなくなって速度が落ちる。ただ、電源を切るとメモリの中身は消えるので、不安定になってもパソコンを再起動すれば治る。
GB(容量)

ギガバイト。データやメモリの量の単位。メモリはデータ置き場なので、単純に容量が大きいほど動作の安定化に繋がる。不要になったデータは随時メモリから取り除かれるので、一般の作業ではそうそう不足しないが、そもそも少なかったり、大きなデータや写真をまとめて扱ったり、映像編集したり、ゲームを長く遊んだりすると不足してくる。
DDR4

DDR(ダブル データ レート)という種類のメモリの第4世代。2014年以降、長く主流を務めていた。DDR4-3200と書かれていたら、DDR4で速度が3200のもの。数値が大きいほど高速だが、どのメモリを使えるかはCPU次第。
2025年から2026年にかけて生産が終了することになっていたが、AI需要によるメモリの記録的な不足が発生し、もうしばらく作られることになった。
PC4
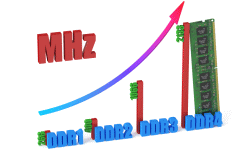
これもメモリの種類。DDR4のこと。PC4-25600と書かれていたら、PC4(DDR4)で速度が25600の意味。DDR4-3200とPC4-25600は同じもので、初代のDDRメモリを基準にして、DDR2で速度が2倍、DDR3でまた2倍、DDR4でさらに2倍になったので、3200x2x2x2で25600ということなのだが、モノは一緒。一応、こちらの方が実際の最大速度を表している。
DDR5

2022年から普及が始まった第5世代のDDRメモリ。近年のCPUでなければ使用できない。データを扱う速度はさらに倍になっているが、有効かは用途により、一般的な作業やゲームではDDR4と大差ないことが多い。一方、画像加工や動画エンコード、データ圧縮などでは影響が大きい。
2025年後半から起こったAI需要による記録的なメモリ不足により、価格が高騰している。
LPDDR
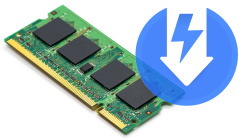
省電力機能を強化した小型のDDRメモリで、主にノートパソコンやタブレット、スマホなどに使われている。高価だが独自の進化をしていて、普通のDDRメモリより高速なものもある。近年のものは、もはや普通のDDRメモリとは別物。末尾にXが付いているものは改良型。
デュアルチャネル
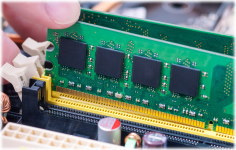
2本のメモリにデータを分散し、処理を高速化させる技術。デュアルチャンネルや2チャネルと表記されていることもある。16GBのメモリで「8GBx2」と書かれている場合、8GBメモリを2本使ってデュアルチャネルで使用していることを示す。この技術の普及により、メモリが1本だと速度に劣る。
シングルランク(1R)、デュアルランク(2R)

1枚のメモリの中身を2つのグループに分けているものをデュアルランクと言い、略して「2R」と表記される。4つの場合はクアッドランクで「4R」。これらが登場したことで、1枚が1グループの場合はシングルランクと呼ばれ「1R」と表記されるようになった。
グループが多い方がアクセスの速度が上がるが、CPUによって使えるランクの総数が異なる。
以前は気にする必要なかったが、2017年頃から CPU が Ryzen の場合、ランクによって使えるメモリや速度が変わるようになった。
ヒートシンク

放熱板のこと。メモリはそこまで高熱にならないので放熱板は必要ないが、装飾や付加価値として付いている場合がある。また、CPUクーラーが水冷だと風がメモリに当たらず冷えづらいので、その対策として付けることもある。
DIMM / SO-DIMM
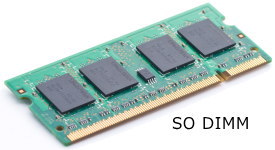
DIMMはメモリのことだが、大きさの意味でも使われる。デスクトップパソコンは普通のDIMMを、ノートパソコンには小型のSO-DIMMを使用する。スリム型やモニター一体型のパソコンにSO-DIMMが使われることもある。ちなみにSOはスモールアウトライン(小型)の略。
SDRAM / RAM

普通のメモリのこと。種類の呼び名だったが、今はほとんどSDRAMなので気にする必要はない。RAMとはメモリのことで、DDRメモリの正式名はDDR-SDRAM。
直付け / オンボード
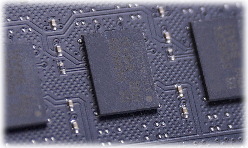
基板(マザーボード)にくっついていて外せないメモリ。くっつけてしまえば着脱部が必要なくなるので省スペースかつコストダウンになるし、電線の距離が短くなるのでより高速化するが、もちろんメモリの交換はできなくなる。スマホやタブレットはこれが一般的で、小型PCやノートパソコンにも直付けのものがある。
LPDDR5 と LPDDR5X は直付け用メモリである。
メインメモリ
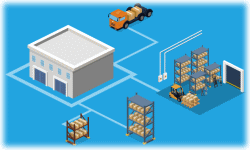
普通のメモリのこと。グラフィック機能専用のメモリであるビデオメモリ(VRAM)、CPU内のメモリであるキャッシュメモリなどがあるため、それとの区別のために本体のメモリをメインメモリと呼んだりする。
なお、CPU内蔵グラフィック機能はメインメモリの一部をビデオメモリに転用するので、転用中はその分だけメインメモリが減る。
スマホのメモリについて

用語ではないが注意事項として。
スマホはメモリの量がギリギリの場合が多いので、メモリの搭載量が性能に大きく関わることが多い。
そのためメモリが多いほど動作が速いんだと思っている人も多いが、パソコンのメモリは普通そこまでカツカツではなく、またメモリはあくまでデータ置き場であり、パソコンの場合メモリが多い=速いということにはならない。
搭載量や使用状況にもよるが、あくまで安定性に影響するものである。
また Windows、iPhone、Android でそれぞれメモリの必要量が異なり、iPhone(iOS)は必要メモリが少なく、多様な環境に対応しているWindowsやAndroidは使用メモリが多い。
そのため「iPhoneはメモリが少ないから性能が低い。メモリが多いAndroidの方が高性能」みたいな話も間違っており、快適なメモリ量はシステム(OS)によって異なる。
※ビデオメモリなど、グラフィック関連については こちら を、長期的にデータを記録するストレージについては こちら をご覧ください。
